
|
海から受ける多大な恩恵
環境を守るウェーブを!
B&G「少年の船」団長森田浩二
今年の7月20日は初めて「海の日」が国民の祝日となりました。皆さんは海というと、何を想像されるでしょう。海水浴、満干狩り、潮騒、サーフィンなどいろいろと頭に浮かんでくるかもしれません。その海が今大変なことになっているのです。
今から35年前、ソ連の宇宙船ボストークに乗っだガガーリンという宇宙飛行士が一枚の写真在共にメッセージを送ってました。それが「地球は青かった」という、後々まで残る有名な言葉です。つまり7割を占める青い海の地球を見た第一印象だったのでしょう。私たちも写真を見て、あー地球はきれいだなーと思いました。
あれから35年経ち、今では宇宙からの写真も珍しくなくなってきましたが、この地球の姿は大きく様変りしてきているのです。専門家の意見ですと、海は汚染され、森林も伐採されて線が減っている。あれほど美しかった地球が死の星になる可能性もあるのです。もし海が言葉を話せるとしたら、「人間よこんなに私をイジメないで」と言っているのではないでしょうか。
海は偉大なる母といわれるのはご存じだと思います。すべての生きものは海によって生かされているといってもいいでしょう。人間が生きていくには何が必要でしょうか。水も酸素も、まず海から始まり、雨となり、植物を育て、酸素を作り出しているのです。
日本は資源を輸入に頼っています。その運送方法の大部分は海を走る船で運んでいるのです。
まもなく別世紀になろうとしています。19世紀は産業革命が起こりました。20世紀はどんな時代だったと後世の人たちはいうでしょうか。度重なる戦争によって、あるいは高度な文明の発達によって、自然を破壊した世紀といわれないでしょうか。世界の学者が予想するところでは、21世紀は、自然環境など20世紀に壊されたものを保繕、再生する世紀になるだろうということです。
先程言ったように海からは多大な恩恵を受けているわけです。ですから「海の日」には、海について真剣に考え、皆さんにはこれからの海の環境を守る担い手となる大きなウェーブを起こしてもらいたいと思います。 (抜粋)

ふじ丸はグアム、サイパンを出てから太平洋を一路北上してきましたが、皆さんもすでにご存じのようにたくさんの島々を通ってきました。北マリアナ諸島、そして硫黄島、孀婦岩、天然記念物のあほう鳥の営巣地である鳥島は、島全体も天然記念物に指定されています。もちろん誰も入ることはできません。こういった島々は船で旅行する以外なかなか見ることはできません、皆さんにとって、私たち船乗りについても知る機会があまりないかもしれません。
私は船に乗って30年になります。最初は訓練生として、世界最大級の海王丸という帆船に乗りました。学生が500人位乗って太平洋のバンクーバー、サンフランシスコ、ハワイをまわります。
ここで私たちは船乗りの卵として、船乗り魂・シーマンシップをたたきこまれました。
シーマンシップには、二つの意味があります。その一つはスピリット、船員道みたいなものですね。もう一つは船を繰る技術・スキルです。
商船大学の卒業の時にこの練習船で、約6ヵ月の航海をします。一部屋に8人。共同生活ですから、まず他人に迷惑をかけないことを教えこまれます。この「少年の船」の今の皆さんと同じです。
ぶじ丸は時速30キロ位で走っていますが、この帆船は18キロ前後。ゆっくり走ります。
積み込む水は約500トン。全員でこの量を一か月間もたせなくてはいけません。一日一人2リットル。昔風にいうと一升ビン一本。現在ぶじ丸で皆さんがどの位の水を使っているかというと、一人約400リットルです。この中にはトイレとかシャワーも含まれますが。練習船ではこの2リットルで、歯を展き、顔を洗い、もちろん飲み水としても使います。
お風呂は海水ですから少しヌルヌルします。仕方ないのでこの水を少し使って体を拭きます。洗濯はスコールがくるのを待って、全員デッキに出て洋服を体に着たまませっけんをつけて洗濯をするんです。水だけでなく物を大切にすることを心底教えられます。
帆船ですから高いマストに登らなくてはなりません。一番上は海面から40メートルもありますが、高所恐怖症なんていってられません。でも結構恐いんです。この他、六分後を使って船の位置を訓べる研修をしたりもします。今は人工衛星を使って船の位置を把握していますが、もし受信機が壊れても、太陽と月と星が出ていれば、こんな原始的な方法でも船の位置がわかることができるわけです。
以上は私の30年前の話ですが、物を大切にする気持ち、その場における卓越した技術、能力といったシーマンシップの心意気は、現在のこのふじ丸でもそれぞれの持ち場で発揮してくれているはずです。(抜粋)
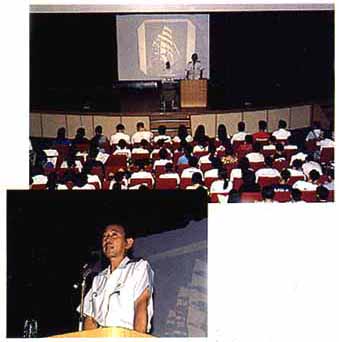
前ページ 目次へ 次ページ
|

|